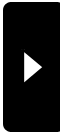2014年10月30日
戦争遺跡調査『三浦集落』
平成26年10月8日(水)
加計呂麻島民泊協議会さんと戦争遺跡の合同調査を行いました。
加計呂麻島民泊協議会は、
・加計呂麻島の民家に泊まり様々な体験を行う
・島の歴史や文化に触れ合う
・シマの素材を使ってモノづくりをする
ということを目的とし、2012年から活動されています。
これまで、学生サークルの方々などの利用があり、加計呂麻島の歴史や文化を学び体験する場として活用されています。
加計呂麻島在住の方々や現地ガイド、山や植物の専門の先生方も含め12名の参加となりました。

この日、向かった先は、加計呂麻島の『三浦集落』
第十八震洋隊が配備された『呑之浦』から、湾を二つ隔てた湾奥のひっそりとした場所に位置します。
2000年には、仲田浦で、第十七震洋隊(三浦基地)の「格納壕」が6つ確認されています。
今回の調査地は、なかなか歩いては行けない場所にあるので、
調査は、大潮の干潮時間に行われました。

干潮時間帯でも、この水位。
崖を登ったり下ったり。

滑らないように皆で声をかけて進みます。
海から見たらこのような風景ですが、

このアダンなどの林の奥に
二つの『格納壕』を確認。


壕の方位や略測も行いました。

軽く叩いてみると、床下の音に違和感があり、空洞になっているような場所もあり、
レールなどがあったのかも?と調査メンバーで推測しました。
三つ目は、離れた場所で確認できました。

入口付近は、残念ながら大量のゴミが置かれていました。
しかし、奥に入ると、内部の状態に驚きました。

ほぼ崩れることなく、当時のままで保持されている状態でした。

壕を補強していたと思われる“木材”の破片が所々で見られました。

今回の調査では、4つの『格納壕』を確認することができました。

これまで、入ったこともない場所にどんどん入っていき、予想を超える調査量となりました。
観光地として整備されている『呑之浦』と同じような環境にある湾内に、
これだけの壕があったことに、驚きました。
今回は、民泊協議会の皆さんと共に調査をすることができました。
加計呂麻島在住の方々は『まずは、自分たちが知ること』と、とても勉強熱心。
その姿勢に感銘を受けました。
人が多ければ、調査地点も多くなり、様々なことに気が付きます。
こうして地元を知る地域の皆さんと協力して調査ができることは、とても素晴らしいことだと実感しました。
2014.10.08
加計呂麻島 三浦集落
埋蔵文化財調査員 正智子
加計呂麻島民泊協議会さんと戦争遺跡の合同調査を行いました。
加計呂麻島民泊協議会は、
・加計呂麻島の民家に泊まり様々な体験を行う
・島の歴史や文化に触れ合う
・シマの素材を使ってモノづくりをする
ということを目的とし、2012年から活動されています。
これまで、学生サークルの方々などの利用があり、加計呂麻島の歴史や文化を学び体験する場として活用されています。
加計呂麻島在住の方々や現地ガイド、山や植物の専門の先生方も含め12名の参加となりました。

この日、向かった先は、加計呂麻島の『三浦集落』
第十八震洋隊が配備された『呑之浦』から、湾を二つ隔てた湾奥のひっそりとした場所に位置します。
2000年には、仲田浦で、第十七震洋隊(三浦基地)の「格納壕」が6つ確認されています。
今回の調査地は、なかなか歩いては行けない場所にあるので、
調査は、大潮の干潮時間に行われました。

干潮時間帯でも、この水位。
崖を登ったり下ったり。

滑らないように皆で声をかけて進みます。
海から見たらこのような風景ですが、

このアダンなどの林の奥に
二つの『格納壕』を確認。


壕の方位や略測も行いました。

軽く叩いてみると、床下の音に違和感があり、空洞になっているような場所もあり、
レールなどがあったのかも?と調査メンバーで推測しました。
三つ目は、離れた場所で確認できました。

入口付近は、残念ながら大量のゴミが置かれていました。
しかし、奥に入ると、内部の状態に驚きました。

ほぼ崩れることなく、当時のままで保持されている状態でした。

壕を補強していたと思われる“木材”の破片が所々で見られました。

今回の調査では、4つの『格納壕』を確認することができました。

これまで、入ったこともない場所にどんどん入っていき、予想を超える調査量となりました。
観光地として整備されている『呑之浦』と同じような環境にある湾内に、
これだけの壕があったことに、驚きました。
今回は、民泊協議会の皆さんと共に調査をすることができました。
加計呂麻島在住の方々は『まずは、自分たちが知ること』と、とても勉強熱心。
その姿勢に感銘を受けました。
人が多ければ、調査地点も多くなり、様々なことに気が付きます。
こうして地元を知る地域の皆さんと協力して調査ができることは、とても素晴らしいことだと実感しました。
2014.10.08
加計呂麻島 三浦集落
埋蔵文化財調査員 正智子
2014年10月25日
埋蔵文化財調査『実久集落』
平成26年10月2日(木)、埋蔵文化財調査で、
加計呂麻島の最西端『実久集落』へ向いました。
豊かな自然 実久ブルーの海 白い砂浜

この日は、クガツクンチ(旧暦九月九日)
実久三次郎神社大祭も開催されていました。

加計呂麻島といえば、“諸鈍シバヤ”ですが、
源氏と平家の伝説が残るこの加計呂麻島で、
同じ日にお祭りが開催されていることは、まだまだ知られていないことかもしれません。
加計呂麻島の
西(実久)では、源為朝の子『実久三次郎』が実久三次郎神社に、
東(諸鈍)では、『平資盛』が大屯神社に祀られています。
さらに、この実久集落は、戦争遺跡も多く残っている場所でもあります。
今回は、集落内の埋蔵文化財調査を行いました。

兵舎跡

貯水施設?
*実久戦跡調査は以前にも同行調査を行いました。記事は、コチラ
*構築された年代などは、『瀬戸内町の戦争遺跡について』で記しています。
埋蔵文化財調査では、とにかく下をみて歩きます。
集落内の畑や空き地には、すでに

新しい砂(土)が入っている土地もあります。
別の場所から土を持ってきている場合もあるので、このような場所で採集した遺物の判断は難しいそうです。

擂鉢(すりばち)のカケラ
今回、表面採集した遺物

土器(不明)、青磁(中国産)、褐釉陶器(中国産)、青花(中国産)、本土産陶器、沖縄産陶器、
本土産陶磁器、貝、ガラス
今回の埋蔵文化財調査によって実久集落では、少なくとも中世~近代の遺物を採集することができました。
≪実久集落 番外編≫
実久といえば、

珊瑚の石垣
ハカラメ(葉から芽)がとてもかわいいアクセントに。
場所場所で、石垣の積み方が違うのも面白かったですよ。

五右衛門風呂跡
(隊長が欲しいとつぶやいていました)
関連記事はこちら
一日(下ばかり見て)歩き疲れて、ふと海側をみると、デッキが!

実久には泳ぎに来るべきですね(涙)

シマ(集落)を歩いているといつもおもう。
「シマの美しい風景」
シマに暮らす人たちが、大事に手をかけているからこそだと感じます。
「シマを守る美しさ」
私たちがお邪魔するときは、ルールを守ってシマの風景を楽しみたいですね。
この日は、お祭りに来られていた方々からも、貴重なお話を聞くことができました。
シマ育ちではないけれど、島に帰って来たと思える雰囲気がこのシマの魅力
温かい空間にて調査をすることができました。
ありがとうございました。
2014.10.02
加計呂麻島実久集落
埋蔵文化財調査員 正智子
加計呂麻島の最西端『実久集落』へ向いました。
豊かな自然 実久ブルーの海 白い砂浜

この日は、クガツクンチ(旧暦九月九日)
実久三次郎神社大祭も開催されていました。

加計呂麻島といえば、“諸鈍シバヤ”ですが、
源氏と平家の伝説が残るこの加計呂麻島で、
同じ日にお祭りが開催されていることは、まだまだ知られていないことかもしれません。
加計呂麻島の
西(実久)では、源為朝の子『実久三次郎』が実久三次郎神社に、
東(諸鈍)では、『平資盛』が大屯神社に祀られています。
さらに、この実久集落は、戦争遺跡も多く残っている場所でもあります。
今回は、集落内の埋蔵文化財調査を行いました。

兵舎跡

貯水施設?
*実久戦跡調査は以前にも同行調査を行いました。記事は、コチラ
*構築された年代などは、『瀬戸内町の戦争遺跡について』で記しています。
埋蔵文化財調査では、とにかく下をみて歩きます。
集落内の畑や空き地には、すでに

新しい砂(土)が入っている土地もあります。
別の場所から土を持ってきている場合もあるので、このような場所で採集した遺物の判断は難しいそうです。

擂鉢(すりばち)のカケラ
今回、表面採集した遺物

土器(不明)、青磁(中国産)、褐釉陶器(中国産)、青花(中国産)、本土産陶器、沖縄産陶器、
本土産陶磁器、貝、ガラス
今回の埋蔵文化財調査によって実久集落では、少なくとも中世~近代の遺物を採集することができました。
≪実久集落 番外編≫
実久といえば、

珊瑚の石垣
ハカラメ(葉から芽)がとてもかわいいアクセントに。
場所場所で、石垣の積み方が違うのも面白かったですよ。

五右衛門風呂跡
(隊長が欲しいとつぶやいていました)
関連記事はこちら
一日(下ばかり見て)歩き疲れて、ふと海側をみると、デッキが!

実久には泳ぎに来るべきですね(涙)

シマ(集落)を歩いているといつもおもう。
「シマの美しい風景」
シマに暮らす人たちが、大事に手をかけているからこそだと感じます。
「シマを守る美しさ」
私たちがお邪魔するときは、ルールを守ってシマの風景を楽しみたいですね。
この日は、お祭りに来られていた方々からも、貴重なお話を聞くことができました。
シマ育ちではないけれど、島に帰って来たと思える雰囲気がこのシマの魅力
温かい空間にて調査をすることができました。
ありがとうございました。
2014.10.02
加計呂麻島実久集落
埋蔵文化財調査員 正智子
2014年10月22日
諸数集落『ミキ作り』 クガツクンチ
平成26年10月2日(水)は、旧暦9月9日
加計呂麻島の諸数集落は、伝統行事『クガツクンチ』のために、『ミキ』を手作りしている数少ない集落です。
今回の『諸数のミキ作り』レポートを、諸数在住の須崎まさこさんに紹介していただきます。
* * *
奄美大島の昔から続けてられる年中行事の中に、
旧暦9月9日(クガツクンチ)があります。

旧暦9月9日には、各集落(地)の守護神(産土神)を参拝するのですが、
その際に「ミキ」をお供えします。
ミキの作り方は、各集落でも違うそうなのですが、
私の住んでいる加計呂麻島の『諸数集落』では、
現在でも集落の婦人たちが集まり、ミキ作りが行われています。
今回は、諸数の『ミキ作り』をご紹介します。
“ミキは、発酵飲料なので二晩寝かせる”と言うのが、昔からの習わしだそうです。
今年は、10月2日水曜日が旧暦9月9日にあたります。
この日に合わせて、9月30日の午前中にミキ作りが始まりました。
【其の一】
諸数では、朝できたてのお粥を持って集会所に集まることから始まります。

持ち寄ったお粥を、ひとつの大きな鍋に移します。
【其のニ】
お粥の中に分量の白糖を入れる。

【其の三】
お粥があたたかいので、すぐ溶けるので、よく交ぜてなじませる。

【其の四】
分量のサツマイモを薄くスライスして水でさらす。

ザルにとって水を切っておく。

サツマイモは、発酵させるために使うのですが、
この時期の気温などによって分量を調整したりしてるそうです。
涼しければ、サツマイモの量を増やし、発酵を促進させると言った感じですね。
【其の五】
水を切ったサツマイモをミキサーにかける。

【其の六】
ミキサーにかけたサツマイモの汁をお粥の中に投入してよく交ぜる。

【其の七】
全て合わせたお粥を少しづつミキサーにかける。

【其の八】
ミキサーにかけたものをザルで裏ごしする。

【其の九】
全てのお粥の裏ごしが終わったら、最後によく交ぜておく。

これで下ごしらえは終了。
【其の十】
ミキを瓶に移します。とてもなめらかでキレイな乳白色です。

【其の十一】
瓶の蓋には、バシャの葉(バナナの葉)を使います。

【其の十二】
バシャの葉をとめておくのには、藁で左巻きに編んだ縄を使います。

ミキ作りをしている間、敬老の婆ちゃん達が縄を編んでくれます。
神様にお供えする物には全て“左巻き”の縄を使うそうです。
相撲の土俵に使われている、太い縄も左巻きとの事。
これで準備は完了です。
【其の十三】
集落の祠で、二晩寝かせながらのお清め。

旧暦9月9日を待ちます。
* * *
さてここからは、10月2日(旧暦9月9日)のミキをお届けします。
当日の朝から、集落は大忙しです。
朝7時には、男の人達は集落清掃と土俵を整え、女の人達は力飯をつくります。

作業が終わってから、いよいよミキを開けます。
出来栄えはいかに?
縄をほどき、バシャの葉をとると、キレイに発酵して膨らんでました。

少し涼しかったこともあって、もう少し発酵して酸っぱくなっても良かったみたいです。
開けたミキは祠の前で、取り分けて頂きました。
この後は、集落の青年・壮年と産土神にお参りし、ミキをお供えしてきました。

この後は旧暦9月9日を祝い、
朝作った力飯を青年が土俵でお清めして、宴会が始まります。
諸数集落住民が集って続けられている年中行事の一つ
『クガツクンチ』


毎年こうして、
ミキを飲むことから始まり、食事をして語らい、お酒を飲んで、カラオケしたりして楽しみます。
少ない人数ですが、これからもずっと引き継いで続けていきたいですね。
『集落に伝わるミキ作り』をレポートしてみましたが、
昔は、白米も少なかったり、上白糖やミキサーなどの道具もなかったため
芋の分量が多かったり、黒糖を使ったりして作っていたそうです。
その為、粒も残って色のついたミキだったということです。
伝統は続きながら、時代と共に使う食材が変化しているようです。
レポート
諸数在住 須崎まさこ
* * *
島の人々が楽しみにしている行事のひとつでもあるクガツクンチ
同じ日には、諸鈍シバヤや実久三次郎大祭などが行われています。
集落によって、現在もこのように行事が続いていることは、シマの宝、まさにヒギャジマン!
記録をとることで、住むシマの伝統の変化が見えてくることは、面白いことかもしれませんね。
須崎さんレポートありがとうございました。
2014.10.02(旧暦9月9日)
加計呂麻島 諸数集落
加計呂麻島の諸数集落は、伝統行事『クガツクンチ』のために、『ミキ』を手作りしている数少ない集落です。
今回の『諸数のミキ作り』レポートを、諸数在住の須崎まさこさんに紹介していただきます。
* * *
奄美大島の昔から続けてられる年中行事の中に、
旧暦9月9日(クガツクンチ)があります。

旧暦9月9日には、各集落(地)の守護神(産土神)を参拝するのですが、
その際に「ミキ」をお供えします。
ミキの作り方は、各集落でも違うそうなのですが、
私の住んでいる加計呂麻島の『諸数集落』では、
現在でも集落の婦人たちが集まり、ミキ作りが行われています。
今回は、諸数の『ミキ作り』をご紹介します。
“ミキは、発酵飲料なので二晩寝かせる”と言うのが、昔からの習わしだそうです。
今年は、10月2日水曜日が旧暦9月9日にあたります。
この日に合わせて、9月30日の午前中にミキ作りが始まりました。
【其の一】
諸数では、朝できたてのお粥を持って集会所に集まることから始まります。

持ち寄ったお粥を、ひとつの大きな鍋に移します。
【其のニ】
お粥の中に分量の白糖を入れる。

【其の三】
お粥があたたかいので、すぐ溶けるので、よく交ぜてなじませる。

【其の四】
分量のサツマイモを薄くスライスして水でさらす。

ザルにとって水を切っておく。

サツマイモは、発酵させるために使うのですが、
この時期の気温などによって分量を調整したりしてるそうです。
涼しければ、サツマイモの量を増やし、発酵を促進させると言った感じですね。
【其の五】
水を切ったサツマイモをミキサーにかける。

【其の六】
ミキサーにかけたサツマイモの汁をお粥の中に投入してよく交ぜる。

【其の七】
全て合わせたお粥を少しづつミキサーにかける。

【其の八】
ミキサーにかけたものをザルで裏ごしする。

【其の九】
全てのお粥の裏ごしが終わったら、最後によく交ぜておく。

これで下ごしらえは終了。
【其の十】
ミキを瓶に移します。とてもなめらかでキレイな乳白色です。

【其の十一】
瓶の蓋には、バシャの葉(バナナの葉)を使います。

【其の十二】
バシャの葉をとめておくのには、藁で左巻きに編んだ縄を使います。

ミキ作りをしている間、敬老の婆ちゃん達が縄を編んでくれます。
神様にお供えする物には全て“左巻き”の縄を使うそうです。
相撲の土俵に使われている、太い縄も左巻きとの事。
これで準備は完了です。
【其の十三】
集落の祠で、二晩寝かせながらのお清め。

旧暦9月9日を待ちます。
* * *
さてここからは、10月2日(旧暦9月9日)のミキをお届けします。
当日の朝から、集落は大忙しです。
朝7時には、男の人達は集落清掃と土俵を整え、女の人達は力飯をつくります。

作業が終わってから、いよいよミキを開けます。
出来栄えはいかに?
縄をほどき、バシャの葉をとると、キレイに発酵して膨らんでました。

少し涼しかったこともあって、もう少し発酵して酸っぱくなっても良かったみたいです。
開けたミキは祠の前で、取り分けて頂きました。
この後は、集落の青年・壮年と産土神にお参りし、ミキをお供えしてきました。

この後は旧暦9月9日を祝い、
朝作った力飯を青年が土俵でお清めして、宴会が始まります。
諸数集落住民が集って続けられている年中行事の一つ
『クガツクンチ』


毎年こうして、
ミキを飲むことから始まり、食事をして語らい、お酒を飲んで、カラオケしたりして楽しみます。
少ない人数ですが、これからもずっと引き継いで続けていきたいですね。
『集落に伝わるミキ作り』をレポートしてみましたが、
昔は、白米も少なかったり、上白糖やミキサーなどの道具もなかったため
芋の分量が多かったり、黒糖を使ったりして作っていたそうです。
その為、粒も残って色のついたミキだったということです。
伝統は続きながら、時代と共に使う食材が変化しているようです。
レポート
諸数在住 須崎まさこ
* * *
島の人々が楽しみにしている行事のひとつでもあるクガツクンチ
同じ日には、諸鈍シバヤや実久三次郎大祭などが行われています。
集落によって、現在もこのように行事が続いていることは、シマの宝、まさにヒギャジマン!
記録をとることで、住むシマの伝統の変化が見えてくることは、面白いことかもしれませんね。
須崎さんレポートありがとうございました。
2014.10.02(旧暦9月9日)
加計呂麻島 諸数集落
2014年10月18日
埋蔵文化財調査『西阿室集落』
平成26年10月1日(水)、埋蔵文化財調査で、
加計呂麻島の『西阿室集落』へと向かいました。

『グリヤマ』より集落を一望

ミャーのガジュマルは、圧巻!
下を見て歩いていると、カムィヤキ発見!

カムィヤキは、本土の須恵器に似ていたため『類須恵器』と呼ばれていました。
徳之島で窯跡が発見されたため、カムィヤキは徳之島で焼かれたものと考えられています。

歩きに歩き、浜の端っこまできました。戦時中の壕も発見!
貝殻の採集や砂の採取も行いました。
今回、表面採集した遺物

土器、カムィヤキ、白磁(中国産)、青磁(中国産)、本土産陶器、
沖縄産陶器、本土産陶磁器、鉄滓、貝 など
今回の埋蔵文化財調査によって、西阿室集落では古代~近代までの遺物を採集することができました。
≪西阿室集落 番外編≫
今回の調査中には、冬鳥の

『ミサゴ』を発見しました!
さらに、こちらも冬鳥の

『サシバ』も!
さらに、

オオウナギが川にいるなんて!!
集落散策をしていると、

管理の行き届いた美しさ
訪れた人を楽しませるシマの雰囲気が、最高ですね!
はやくも冬の到来を知らせる野鳥にも出会えて、
季節の移り変わりを感じることができた調査となりました。
参考文献
「瀬戸内町の文化財をたずねて」 瀬戸内町教育委員会
2014.10.01
加計呂麻島 西阿室集落
埋蔵文化財調査員 正智子
加計呂麻島の『西阿室集落』へと向かいました。

『グリヤマ』より集落を一望

ミャーのガジュマルは、圧巻!
下を見て歩いていると、カムィヤキ発見!

カムィヤキは、本土の須恵器に似ていたため『類須恵器』と呼ばれていました。
徳之島で窯跡が発見されたため、カムィヤキは徳之島で焼かれたものと考えられています。

歩きに歩き、浜の端っこまできました。戦時中の壕も発見!
貝殻の採集や砂の採取も行いました。
今回、表面採集した遺物

土器、カムィヤキ、白磁(中国産)、青磁(中国産)、本土産陶器、
沖縄産陶器、本土産陶磁器、鉄滓、貝 など
今回の埋蔵文化財調査によって、西阿室集落では古代~近代までの遺物を採集することができました。
≪西阿室集落 番外編≫
今回の調査中には、冬鳥の

『ミサゴ』を発見しました!
さらに、こちらも冬鳥の

『サシバ』も!
さらに、

オオウナギが川にいるなんて!!
集落散策をしていると、

管理の行き届いた美しさ
訪れた人を楽しませるシマの雰囲気が、最高ですね!
はやくも冬の到来を知らせる野鳥にも出会えて、
季節の移り変わりを感じることができた調査となりました。
参考文献
「瀬戸内町の文化財をたずねて」 瀬戸内町教育委員会
2014.10.01
加計呂麻島 西阿室集落
埋蔵文化財調査員 正智子
2014年10月10日
『実久三次郎神社大祭』
平成26年10月2日(水)旧暦9月9日(クガツクンチ)
加計呂麻島実久集落にて、『実久三次郎神社大祭』が開催されました。
現在は、敬老会も兼ねた豊年祭としても行われています。

祭りは、この実久三次郎神社から始まります。
保元の乱で敗れ、伊豆大島に流された鎮西八郎為朝は、
伊豆大島から琉球列島に渡ったという伝説があります。
この神社は、この鎮西八郎為朝とシマの女性との間に生まれた実久三次郎を祀っています。

社殿で、ミキ開きの儀式が行われた後、訪れた人たちが順番に参拝をします。
参拝を終えると、社殿の横で、ミキとヒモン(干物)を頂きました。
やっぱり手作りのミキは美味しい!

神社境内には、仮の土俵が作られています。

ここでは、廻しをつけた男たちが、三番相撲をとります。

その後、神人役を先頭に実久三次郎の御霊(位牌)を捧げ持ち、ホラ貝を吹きながら神社をあとにします。

神人役が塩で道を祓いながら、カミミチを進んでいき、力士たちも行列をつくりあとに続きます。

公民館前の大きなガジュマルの木の下で、塩でお祓いをしながら3周まわり、
“ヨイヤ~ヨイヤ~ヨイヤ~”の掛け声で、土俵のある公民館広場へ入場していきます。

“振り出し”
子供たちも加わり、終始なごやかな雰囲気に包まれていました。
今回、神社から始まり、カミミチを通って行う儀式を、私自身初めて見ることができました。
♪ ここは、加計呂麻・祭りシマ~ ♫
*余興の歌・加計呂麻巡りより
ということで、
島唄、婦人の踊り、相撲、フラダンス、歌(替え歌)などの余興がありました。
島人は、ほんとに芸達者さんたちばかり!
そんな中でも、
薩川小中学校の子供たちの活躍が、この祭りを特に盛り上げていました。
オープニングは、『薩川太鼓』


『実久棒踊り』




かっこいい太鼓のリズムと伝統の棒踊り!
元気な子供たち、熱心な先生、父兄の方々が息を合わせて実演。
来年は、青年団の『棒踊り』の勇姿もみたいですね。
祭りの最後は、土俵を囲み、『八月踊り』


子供たちが、歌詞を一生懸命に歌っていました。頼もしい!
地域によって、中心になる年代が違うというのもまた面白いですね。

祭りの最後は、〆の六調。
シマの先生の指笛が響き渡り、会場は一気に盛り上がり、胸が高鳴りました!
子供たちの表情も緊張がとれて、とてもいい顔をしていました。
今回は、埋蔵文化財調査も兼ねて実久集落にお邪魔させていただきました。
この豊かな自然と美しいムラの風景がいつまでも続きますように。
参考文献
松原武実 2004 『奄美 加計呂麻島のノロ祭祀』
2014.10.02
加計呂麻島実久集落
埋蔵文化財調査員 正智子
加計呂麻島実久集落にて、『実久三次郎神社大祭』が開催されました。
現在は、敬老会も兼ねた豊年祭としても行われています。

祭りは、この実久三次郎神社から始まります。
保元の乱で敗れ、伊豆大島に流された鎮西八郎為朝は、
伊豆大島から琉球列島に渡ったという伝説があります。
この神社は、この鎮西八郎為朝とシマの女性との間に生まれた実久三次郎を祀っています。

社殿で、ミキ開きの儀式が行われた後、訪れた人たちが順番に参拝をします。
参拝を終えると、社殿の横で、ミキとヒモン(干物)を頂きました。
やっぱり手作りのミキは美味しい!

神社境内には、仮の土俵が作られています。

ここでは、廻しをつけた男たちが、三番相撲をとります。

その後、神人役を先頭に実久三次郎の御霊(位牌)を捧げ持ち、ホラ貝を吹きながら神社をあとにします。

神人役が塩で道を祓いながら、カミミチを進んでいき、力士たちも行列をつくりあとに続きます。

公民館前の大きなガジュマルの木の下で、塩でお祓いをしながら3周まわり、
“ヨイヤ~ヨイヤ~ヨイヤ~”の掛け声で、土俵のある公民館広場へ入場していきます。

“振り出し”
子供たちも加わり、終始なごやかな雰囲気に包まれていました。
今回、神社から始まり、カミミチを通って行う儀式を、私自身初めて見ることができました。
♪ ここは、加計呂麻・祭りシマ~ ♫
*余興の歌・加計呂麻巡りより
ということで、
島唄、婦人の踊り、相撲、フラダンス、歌(替え歌)などの余興がありました。
島人は、ほんとに芸達者さんたちばかり!
そんな中でも、
薩川小中学校の子供たちの活躍が、この祭りを特に盛り上げていました。
オープニングは、『薩川太鼓』


『実久棒踊り』




かっこいい太鼓のリズムと伝統の棒踊り!
元気な子供たち、熱心な先生、父兄の方々が息を合わせて実演。
来年は、青年団の『棒踊り』の勇姿もみたいですね。
祭りの最後は、土俵を囲み、『八月踊り』


子供たちが、歌詞を一生懸命に歌っていました。頼もしい!
地域によって、中心になる年代が違うというのもまた面白いですね。

祭りの最後は、〆の六調。
シマの先生の指笛が響き渡り、会場は一気に盛り上がり、胸が高鳴りました!
子供たちの表情も緊張がとれて、とてもいい顔をしていました。
今回は、埋蔵文化財調査も兼ねて実久集落にお邪魔させていただきました。
この豊かな自然と美しいムラの風景がいつまでも続きますように。
参考文献
松原武実 2004 『奄美 加計呂麻島のノロ祭祀』
2014.10.02
加計呂麻島実久集落
埋蔵文化財調査員 正智子
2014年10月04日
埋蔵文化財分布調査 『嘉徳集落』
平成26年9月24日(水)、埋蔵文化財分布調査を行いました。
今回の調査地は、『嘉徳集落』

嘉徳集落の海岸線は、“黒っぽい砂浜” と “アダンが群生する砂丘” で形成されています。
現在、奄美群島の海岸では、コンクリートの 『堤防』 が主流になっていますが、
嘉徳集落では、現在でも 『アダン群による自然の防波堤』 を見ることができます。
(アダンの映像遺産はこちら)
『瀬戸内町遺跡詳細分布調査報告書』によると、
嘉徳集落では、下記の遺跡が確認されています。
○嘉徳アサト遺跡 (嘉徳遺跡)・・・約4000年前の縄文時代の遺跡
○嘉徳集落遺跡・・・古代~近代の遺跡
***
今回は、集落内の表面採集調査を行いました。

表面採集調査では、
主に畑を歩き、地表面に落ちている遺物【いぶつ】を探します。
なぜかというと、畑では、地面を耕す際に、地中の遺物が地表面に出てくることがあるからです。
畑の耕作で、何気なくよけられた物の中に、
遺物が含まれているということは、
現在、私たちが住んでいる土地に、昔から人が住んでいた証拠でもあるのです。
畑の隅で調査をしていると、青磁を発見!

この青磁は、中国で作られたものです。
こうした調査で得た “遺物” と “採集地点” を地道に調査研究することで、
各時代 の “人々の生活空間” を推測することができます。
今回、表面採集した遺物

土器、中国産の陶磁器,本土産の陶磁器,陶器,貝
今回の埋蔵文化財調査によって嘉徳集落では少なくとも古代~近代の遺物を採集することができました。
表面採集調査の後は、遺物の水洗作業を行います。
水洗作業の様子は、別の機会にご紹介しますね。
また、せとうちなんでも探検隊『シマの紹介』も 調査に並行して更新を行っています。
調査を行いながら、
各集落の紹介も 最新情報を更新していきます。
***
本事業の埋蔵文化財分布調査では、
集落の区長さんに連絡を取り、調査を実施しています。
遺物の採集についても “調査” として行っており、整理・報告後は、公的機関で保管・公開・研究を行います。
個人的な採集は、ぜったいに行わないでください。
【参考文献】
瀬戸内町教育委員会 2005 『瀬戸内町遺跡詳細分布調査報告書』p10~13
***
≪嘉徳集落調査 番外編≫
旧嘉徳小学校を利用している美術館 “ムンユスィ”

看板などが新しくなっていました。
お近くにお寄りの際は、足を運んでみてはいかがでしょうか?
集落内調査中、鳥の鳴き声が。。。

カラスバト
なかなか見ることのできない “カラスバト” なのですが、
この日の嘉徳集落で、見かけた鳥のほとんどが “カラスバト” でした。
さらに、帰りの車中 コロコロっと見えたモノは、

アマミノクロウサギのフン
道の真ん中に転がっていました。
遺物だけでなく、
“集落内の面白いもの” や ”貴重な自然” も発見できた一日となりました。
2014.9.24
瀬戸内町立図書館・郷土館
埋蔵文化財調査員 正智子
今回の調査地は、『嘉徳集落』

嘉徳集落の海岸線は、“黒っぽい砂浜” と “アダンが群生する砂丘” で形成されています。
現在、奄美群島の海岸では、コンクリートの 『堤防』 が主流になっていますが、
嘉徳集落では、現在でも 『アダン群による自然の防波堤』 を見ることができます。
(アダンの映像遺産はこちら)
『瀬戸内町遺跡詳細分布調査報告書』によると、
嘉徳集落では、下記の遺跡が確認されています。
○嘉徳アサト遺跡 (嘉徳遺跡)・・・約4000年前の縄文時代の遺跡
○嘉徳集落遺跡・・・古代~近代の遺跡
***
今回は、集落内の表面採集調査を行いました。

表面採集調査では、
主に畑を歩き、地表面に落ちている遺物【いぶつ】を探します。
なぜかというと、畑では、地面を耕す際に、地中の遺物が地表面に出てくることがあるからです。
畑の耕作で、何気なくよけられた物の中に、
遺物が含まれているということは、
現在、私たちが住んでいる土地に、昔から人が住んでいた証拠でもあるのです。
畑の隅で調査をしていると、青磁を発見!

この青磁は、中国で作られたものです。
こうした調査で得た “遺物” と “採集地点” を地道に調査研究することで、
各時代 の “人々の生活空間” を推測することができます。
今回、表面採集した遺物

土器、中国産の陶磁器,本土産の陶磁器,陶器,貝
今回の埋蔵文化財調査によって嘉徳集落では少なくとも古代~近代の遺物を採集することができました。
表面採集調査の後は、遺物の水洗作業を行います。
水洗作業の様子は、別の機会にご紹介しますね。
また、せとうちなんでも探検隊『シマの紹介』も 調査に並行して更新を行っています。
調査を行いながら、
各集落の紹介も 最新情報を更新していきます。
***
本事業の埋蔵文化財分布調査では、
集落の区長さんに連絡を取り、調査を実施しています。
遺物の採集についても “調査” として行っており、整理・報告後は、公的機関で保管・公開・研究を行います。
個人的な採集は、ぜったいに行わないでください。
【参考文献】
瀬戸内町教育委員会 2005 『瀬戸内町遺跡詳細分布調査報告書』p10~13
***
≪嘉徳集落調査 番外編≫
旧嘉徳小学校を利用している美術館 “ムンユスィ”

看板などが新しくなっていました。
お近くにお寄りの際は、足を運んでみてはいかがでしょうか?
集落内調査中、鳥の鳴き声が。。。

カラスバト
なかなか見ることのできない “カラスバト” なのですが、
この日の嘉徳集落で、見かけた鳥のほとんどが “カラスバト” でした。
さらに、帰りの車中 コロコロっと見えたモノは、

アマミノクロウサギのフン
道の真ん中に転がっていました。
遺物だけでなく、
“集落内の面白いもの” や ”貴重な自然” も発見できた一日となりました。
2014.9.24
瀬戸内町立図書館・郷土館
埋蔵文化財調査員 正智子
2014年09月30日
埋蔵文化財分布調査 「須子茂集落」
平成26年9月17日
「第2回 島案内人育成講座」 が開催されました。
平成26 年度特定離島ふるさとおこし推進事業 「島案内人育成講座」
今回の開催地は加計呂麻島・須子茂集落。

須子茂集落は昔ながらの集落空間が残された集落のひとつ。
ノロ祭祀が行われていたアシャゲやトネヤ,集落の守り神イビガナシが訪れる人を迎えてくれます。
集落内の道は,現在ではめずらしい未舗装道。
砂を踏みしめる音を聞きながら,集落散策をのんびり楽しむことができます。
人一人通るのがやっとの道が突然現れたら,それは “カミミチ” かもしれませんよ。
関連記事はこちら → 「須子茂集落散策 /島案内人講座」
***
今回,埋蔵文化財調査員は島案内人講座に同行し,集落内の埋蔵文化財分布調査を行いました。
まずは,島案内人講座の座学で「須子茂集落の考古学的な歴史」について学びました。

須子茂集落では集落内の道路工事に伴い,発掘調査が行われており(平成16~18年),
弥生時代~近代までの遺物がみつかっています。
座学が終わると,受講生のみなさんは遺物の表面採集にチャレンジです。

場所は集落内・グジヌシ邸宅跡地。
※グジヌシ・・・ノロ神事を行う神役組織の中で唯一の男性神役
みなさん,遺物を見つけようと,ずっと地面とにらめっこしていました。
遺物を見つけたら,学芸員の鼎さん(鼎隊長)に,産地や時代を教えてもらいます。

塀沿いには壺や甕が逆さまに陳列。

この壺や甕も,かつては水を溜めたり,食糧を貯蔵したり大活躍していた遺物です。
遺物を探しながら,集落内を散策すると,立派な門柱(もんちゅう)のあるお宅を発見。

両門柱の上に貝が置いてありますね。
シマでは「魔除け」としてクモガイやスイジガイなどを門柱や玄関付近に置く家があります。
この家の門柱上にはサラサバテイラ(高瀬貝),スイジガイ,クモガイが置かれていました。

この家の塀にはゴホウラが!

ゴホウラはスイショウガイ科の巻貝。
日本では奄美大島以南に生息しています。
ゴホウラは特に弥生時代において北部九州を中心に,貝輪の原材として需要のあった貝です。
種子島広田遺跡からも多くのゴホウラ製貝輪が,お墓の副葬品として出土しています。
ゴホウラは須子茂集落の発掘調査でも出土している貝ですが,中には一部加工跡のある貝も出土しました。
また,依然行った分布調査でもたくさんのゴホウラが採集されています。
***
昼食後,海岸線でも遺物拾いを行いました。

同時に,現在の海岸で採集可能な貝種調査も行いました。
ここでもゴホウラやホラガイなどを採集することができました。
午後の講座では,集落の辻(つじ)にハブ゙とシャコガイを埋める事例について説明。

「辻」とは,道が十字に交差している地点のことを指します。
須子茂集落では2カ所の辻から,シャコガイに覆われたハブ゙の骨が出土しています。
調査時に出土したシャコガイは約2kgを超える大型のもの。
貝殻・裏をハブの骨にかぶせるように埋設されていました。
(沖縄ではシャコガイのことを俗に「アジケー」と呼び, “魔除け” として門柱などに置くそうです)
シマではハブを “マジムン” と呼び,古くから恐れてきました。
集落などで発見されたハブは撲殺等を行った後,二度と集落内に出没しないようにとの祈りを込め,
魔除けの貝で覆い,辻に埋めたようです。
受講生の中には,
「昔はシマでやっていたよ」という方や,
「つい最近,同じようにして自分の集落の辻にハブを埋めた」という方もいて驚きました。
発掘調査によって証明される民俗事例があることに,みなさん興味深々で話を聞いていました。
集落の道脇,特に辻近くに大きなシャコガイが転がっていたら,
もしかするとハブを辻に埋める民俗事例の名残なのかもしれません。

最後に,
公民館前の広場に集合し,皆さんが拾った遺物を並べてみました。


土器や中国産の陶磁器(青磁,青花),本土産の陶磁器,陶器,沖縄産の陶器,貝 などなど
(中にはごくごく最近の落し物もありましたが)
今回の分布調査によって須子茂集落では古墳時代~近代の遺物を採集することができました。
【参考文献】
鼎丈太郎 2010 「調査区6.9検出 シャコガイ遺構」『須子茂集落遺跡 遺跡範囲確認調査報告書,瀬戸内
町文化財調査報告書』第3集
鼎丈太郎 2012 「奄美大島南部におけるゴホウラ資料 ~表面採集状況及び若干の考察~」『奄美研究の
地表を拓く,第45回琉球大学史学会大会奄美大会 大会資料』
木下尚子 1996 「辟邪の貝 ―しゃこがい考―」『比較民俗研究』第6号 筑波大学比較民俗研究会
黒住耐二 2011 「琉球先史時代人とサンゴ礁資源 ―貝類を中心に―」『先史・原史時代の琉球列島 ~ヒト
と景観~ 考古学リーダー』第19号 六一書房
町健次郎 2010 「調査区6・調査区9出土のハブについて」『須子茂集落遺跡 遺跡範囲確認調査報告書,
瀬戸内町文化財調査報告書』第3集
山里純一 1997 「沖縄の魔除けとまじない ―フーフダ(符札)の研究―」『南島文化叢書 18』 第一書房
2014.9.27
埋蔵文化財調査員 鼎さつき
「第2回 島案内人育成講座」 が開催されました。
平成26 年度特定離島ふるさとおこし推進事業 「島案内人育成講座」
今回の開催地は加計呂麻島・須子茂集落。
須子茂集落は昔ながらの集落空間が残された集落のひとつ。
ノロ祭祀が行われていたアシャゲやトネヤ,集落の守り神イビガナシが訪れる人を迎えてくれます。
集落内の道は,現在ではめずらしい未舗装道。
砂を踏みしめる音を聞きながら,集落散策をのんびり楽しむことができます。
人一人通るのがやっとの道が突然現れたら,それは “カミミチ” かもしれませんよ。
関連記事はこちら → 「須子茂集落散策 /島案内人講座」
***
今回,埋蔵文化財調査員は島案内人講座に同行し,集落内の埋蔵文化財分布調査を行いました。
まずは,島案内人講座の座学で「須子茂集落の考古学的な歴史」について学びました。
須子茂集落では集落内の道路工事に伴い,発掘調査が行われており(平成16~18年),
弥生時代~近代までの遺物がみつかっています。
座学が終わると,受講生のみなさんは遺物の表面採集にチャレンジです。
場所は集落内・グジヌシ邸宅跡地。
※グジヌシ・・・ノロ神事を行う神役組織の中で唯一の男性神役
みなさん,遺物を見つけようと,ずっと地面とにらめっこしていました。
遺物を見つけたら,学芸員の鼎さん(鼎隊長)に,産地や時代を教えてもらいます。
塀沿いには壺や甕が逆さまに陳列。
この壺や甕も,かつては水を溜めたり,食糧を貯蔵したり大活躍していた遺物です。
遺物を探しながら,集落内を散策すると,立派な門柱(もんちゅう)のあるお宅を発見。
両門柱の上に貝が置いてありますね。
シマでは「魔除け」としてクモガイやスイジガイなどを門柱や玄関付近に置く家があります。
この家の門柱上にはサラサバテイラ(高瀬貝),スイジガイ,クモガイが置かれていました。
この家の塀にはゴホウラが!
ゴホウラはスイショウガイ科の巻貝。
日本では奄美大島以南に生息しています。
ゴホウラは特に弥生時代において北部九州を中心に,貝輪の原材として需要のあった貝です。
種子島広田遺跡からも多くのゴホウラ製貝輪が,お墓の副葬品として出土しています。
ゴホウラは須子茂集落の発掘調査でも出土している貝ですが,中には一部加工跡のある貝も出土しました。
また,依然行った分布調査でもたくさんのゴホウラが採集されています。
***
昼食後,海岸線でも遺物拾いを行いました。
同時に,現在の海岸で採集可能な貝種調査も行いました。
ここでもゴホウラやホラガイなどを採集することができました。
午後の講座では,集落の辻(つじ)にハブ゙とシャコガイを埋める事例について説明。
「辻」とは,道が十字に交差している地点のことを指します。
須子茂集落では2カ所の辻から,シャコガイに覆われたハブ゙の骨が出土しています。
調査時に出土したシャコガイは約2kgを超える大型のもの。
貝殻・裏をハブの骨にかぶせるように埋設されていました。
(沖縄ではシャコガイのことを俗に「アジケー」と呼び, “魔除け” として門柱などに置くそうです)
シマではハブを “マジムン” と呼び,古くから恐れてきました。
集落などで発見されたハブは撲殺等を行った後,二度と集落内に出没しないようにとの祈りを込め,
魔除けの貝で覆い,辻に埋めたようです。
受講生の中には,
「昔はシマでやっていたよ」という方や,
「つい最近,同じようにして自分の集落の辻にハブを埋めた」という方もいて驚きました。
発掘調査によって証明される民俗事例があることに,みなさん興味深々で話を聞いていました。
集落の道脇,特に辻近くに大きなシャコガイが転がっていたら,
もしかするとハブを辻に埋める民俗事例の名残なのかもしれません。
最後に,
公民館前の広場に集合し,皆さんが拾った遺物を並べてみました。
土器や中国産の陶磁器(青磁,青花),本土産の陶磁器,陶器,沖縄産の陶器,貝 などなど
(中にはごくごく最近の落し物もありましたが)
今回の分布調査によって須子茂集落では古墳時代~近代の遺物を採集することができました。
【参考文献】
鼎丈太郎 2010 「調査区6.9検出 シャコガイ遺構」『須子茂集落遺跡 遺跡範囲確認調査報告書,瀬戸内
町文化財調査報告書』第3集
鼎丈太郎 2012 「奄美大島南部におけるゴホウラ資料 ~表面採集状況及び若干の考察~」『奄美研究の
地表を拓く,第45回琉球大学史学会大会奄美大会 大会資料』
木下尚子 1996 「辟邪の貝 ―しゃこがい考―」『比較民俗研究』第6号 筑波大学比較民俗研究会
黒住耐二 2011 「琉球先史時代人とサンゴ礁資源 ―貝類を中心に―」『先史・原史時代の琉球列島 ~ヒト
と景観~ 考古学リーダー』第19号 六一書房
町健次郎 2010 「調査区6・調査区9出土のハブについて」『須子茂集落遺跡 遺跡範囲確認調査報告書,
瀬戸内町文化財調査報告書』第3集
山里純一 1997 「沖縄の魔除けとまじない ―フーフダ(符札)の研究―」『南島文化叢書 18』 第一書房
2014.9.27
埋蔵文化財調査員 鼎さつき
2014年09月28日
須子茂小学校 「旧奉安殿」
瀬戸内町,加計呂麻島,須子茂集落。

須子茂集落は,加計呂麻島の西側に位置する集落です。
同集落にある須子茂小学校(現在、休校)。

校内北東部,体育館・裏には 「旧奉安殿」 (以下、奉安殿)が今も残されています。

奉安殿は戦前,主に尋常高等小学校に建てられた建造物。
建物内には,「教育勅語(謄本)」と天皇・皇后陛下の「御真影(写真)」が安置されていました。
瀬戸内町には現在6つの奉安殿が残されています。
『須子茂小学校百周年記念誌」』によると、
須子茂小学校の奉安殿は1939年(S14)9月に竣工したようです。
鉄筋コンクリート造りで,切妻(きりづま)屋根。
入口は平入(ひらいり・屋根の棟と並行な面に出入口がある様式)となっています。

屋根の上にある棟(むね)には千木(ちぎ)と堅魚木(かつおぎ)もあります。

千木は屋根の両端で交叉させた部材,
堅魚木は屋根の上に棟と直角になるように置かれた部材をいいます。
高欄(こうらん)
基壇や階段に設ける装飾性・安全性を兼ねた手すりです。

須子茂小学校・奉安殿の特徴は,「菊の御紋」が現在も残っているということです。
菊の御紋は銅製とのことでした。

【 須子茂小学校・旧奉安殿 】
所在地 : 鹿児島県大島郡瀬戸内町須子茂331
構 造 : 鉄筋コンクリート造,平屋建,基壇付
切妻造
平入
懸魚(げぎょ),鬼板(おにいた),破風板あり
四隅に角柱を型取りし,壁面は洗い出し仕上げ
軒・・・一軒・疎垂木(ひとのき・まばらだるき)
棟・・・千木と堅魚木あり
高欄・・・刎(はね)高欄
扉・・・金属製
入口上部に菊の紋章飾りあり
※「神社建築」を範とする
※「国の登録有形文化財」 2006年(H8)8月 登録
【参考文献】
瀬戸内町立須子茂小学校 1980 『須子茂小学校百周年記念誌』
鹿児島県教育委員会 2004 『鹿児島県の近代化遺産 -鹿児島県近代化遺産総合調査報告書-』
鼎丈太郎 2006 「瀬戸内町の奉安殿」『平成17年度 文化財会報』 奄美文化財保護対策連絡協議会
鹿児島県HP
井上光貞 1998 『図説 歴史散歩辞典』
2014.9.17
加計呂麻島・須子茂集落
埋蔵文化財調査員 鼎さつき
須子茂集落は,加計呂麻島の西側に位置する集落です。
同集落にある須子茂小学校(現在、休校)。
校内北東部,体育館・裏には 「旧奉安殿」 (以下、奉安殿)が今も残されています。
奉安殿は戦前,主に尋常高等小学校に建てられた建造物。
建物内には,「教育勅語(謄本)」と天皇・皇后陛下の「御真影(写真)」が安置されていました。
瀬戸内町には現在6つの奉安殿が残されています。
『須子茂小学校百周年記念誌」』によると、
須子茂小学校の奉安殿は1939年(S14)9月に竣工したようです。
鉄筋コンクリート造りで,切妻(きりづま)屋根。
入口は平入(ひらいり・屋根の棟と並行な面に出入口がある様式)となっています。
屋根の上にある棟(むね)には千木(ちぎ)と堅魚木(かつおぎ)もあります。
千木は屋根の両端で交叉させた部材,
堅魚木は屋根の上に棟と直角になるように置かれた部材をいいます。
高欄(こうらん)
基壇や階段に設ける装飾性・安全性を兼ねた手すりです。
須子茂小学校・奉安殿の特徴は,「菊の御紋」が現在も残っているということです。
菊の御紋は銅製とのことでした。
【 須子茂小学校・旧奉安殿 】
所在地 : 鹿児島県大島郡瀬戸内町須子茂331
構 造 : 鉄筋コンクリート造,平屋建,基壇付
切妻造
平入
懸魚(げぎょ),鬼板(おにいた),破風板あり
四隅に角柱を型取りし,壁面は洗い出し仕上げ
軒・・・一軒・疎垂木(ひとのき・まばらだるき)
棟・・・千木と堅魚木あり
高欄・・・刎(はね)高欄
扉・・・金属製
入口上部に菊の紋章飾りあり
※「神社建築」を範とする
※「国の登録有形文化財」 2006年(H8)8月 登録
【参考文献】
瀬戸内町立須子茂小学校 1980 『須子茂小学校百周年記念誌』
鹿児島県教育委員会 2004 『鹿児島県の近代化遺産 -鹿児島県近代化遺産総合調査報告書-』
鼎丈太郎 2006 「瀬戸内町の奉安殿」『平成17年度 文化財会報』 奄美文化財保護対策連絡協議会
鹿児島県HP
井上光貞 1998 『図説 歴史散歩辞典』
2014.9.17
加計呂麻島・須子茂集落
埋蔵文化財調査員 鼎さつき
2014年09月25日
戦跡調査『西古見』
平成26年9月9日(火)より、埋蔵文化財分布調査の現地調査を開始しました。
今回は、瀬戸内町『西古見』集落へ向かい、
・戦争遺跡の現状調査
・埋蔵文化財の分布調査 を行いました。

『西古見』集落は、古仁屋から約1時間15分ほどの場所に位置し、奄美大島で最西端の集落です。

『曽津高埼灯台【そっこうさきとうだい】』
明治29年11月25日に奄美大島で一番最初に設置・点灯した由緒ある灯台です。
明治27~28年の日清戦争の影響により建設された灯台のひとつ。
(現在の灯台は、昭和63年に建て替えられたものです)
灯台を囲む塀には、第2次世界大戦の終わり頃、アメリカ軍の機銃掃射を受けた弾痕が現在も残っています。

生々しい痕跡は、他にも残されているということですので、今後も調査をしていきたいと思います。
注)灯台までは、舗装されていない道が続きます。
特に悪天候(雨、強風)時や悪天候直後の通行は危険ですので注意が必要です。
こちらは、観光地として整備されている

『掩蓋式観測所【えんがいしきかんそくじょ】』
大正期に作られた観測所は、一部二階で円形の鉄筋コンクリート造の堅個な建物となっています。
内部から見た光景は、加計呂麻島や遠く徳之島、東シナ海を一望できます。
大戦中は大型の望遠鏡が中央台に設置されていたとのこと。
前の窓から敵艦や敵機との距離や方向などを測定して、電話で山中の砲台に連絡をして攻撃をさせるという仕組みがとられていました。

窓の上部に描かれた絵図は、実際の景色と合わせてみても緻密に描かれていますね。
それぞれ島々までの距離が記入されています。

加計呂麻島、江仁屋離、請島

ワレ瀬、須子茂離、夕離、与路島、赤瀬

曽津高崎灯台

大正期に造られた建物は、鉄筋が使われています。
さらに、化粧壁が施されているのも特徴的です。
以前ご紹介した調査地では、鉄筋の代わりに木材が使用されていました。
関連記事 SBI講座『瀬戸内町の戦争遺跡について』
この観測所から離れた場所『池堂【イケドー】』に、
雑草や木々に覆われひっそりと『陸軍兵舎跡』や、『弾薬庫』、『砲台跡』などが残存しています。

『砲台跡』 *今回の調査では雑草に覆われ確認できませんでしたので、以前のデータを使用しました。

『弾薬庫』

昭和20年、西古見の武装解除時の記録には、
『繋船場跡』から砲弾を海中投棄するため、船に積み込んでいる様子が残されています。

『陸軍兵舎跡』
文献資料等を手に、一つずつ戦争遺跡を調査してみると、
建物の役割や他施設との関連が見えてきそうです。
奄美大島で『戦争』が、起こった事実を
どのように、そして、どこまで伝えていくことができるのか?
まだまだ調査は手探り状態ですが、
膨大な資料と照らし合わせながら、
今後も現地調査を進めていきたいと思います。
2014.09.09
瀬戸内町立図書館・郷土館
埋蔵文化財調査員 正 智子
今回は、瀬戸内町『西古見』集落へ向かい、
・戦争遺跡の現状調査
・埋蔵文化財の分布調査 を行いました。

『西古見』集落は、古仁屋から約1時間15分ほどの場所に位置し、奄美大島で最西端の集落です。

『曽津高埼灯台【そっこうさきとうだい】』
明治29年11月25日に奄美大島で一番最初に設置・点灯した由緒ある灯台です。
明治27~28年の日清戦争の影響により建設された灯台のひとつ。
(現在の灯台は、昭和63年に建て替えられたものです)
灯台を囲む塀には、第2次世界大戦の終わり頃、アメリカ軍の機銃掃射を受けた弾痕が現在も残っています。

生々しい痕跡は、他にも残されているということですので、今後も調査をしていきたいと思います。
注)灯台までは、舗装されていない道が続きます。
特に悪天候(雨、強風)時や悪天候直後の通行は危険ですので注意が必要です。
こちらは、観光地として整備されている

『掩蓋式観測所【えんがいしきかんそくじょ】』
大正期に作られた観測所は、一部二階で円形の鉄筋コンクリート造の堅個な建物となっています。
内部から見た光景は、加計呂麻島や遠く徳之島、東シナ海を一望できます。
大戦中は大型の望遠鏡が中央台に設置されていたとのこと。
前の窓から敵艦や敵機との距離や方向などを測定して、電話で山中の砲台に連絡をして攻撃をさせるという仕組みがとられていました。

窓の上部に描かれた絵図は、実際の景色と合わせてみても緻密に描かれていますね。
それぞれ島々までの距離が記入されています。

加計呂麻島、江仁屋離、請島

ワレ瀬、須子茂離、夕離、与路島、赤瀬

曽津高崎灯台

大正期に造られた建物は、鉄筋が使われています。
さらに、化粧壁が施されているのも特徴的です。
以前ご紹介した調査地では、鉄筋の代わりに木材が使用されていました。
関連記事 SBI講座『瀬戸内町の戦争遺跡について』
この観測所から離れた場所『池堂【イケドー】』に、
雑草や木々に覆われひっそりと『陸軍兵舎跡』や、『弾薬庫』、『砲台跡』などが残存しています。

『砲台跡』 *今回の調査では雑草に覆われ確認できませんでしたので、以前のデータを使用しました。

『弾薬庫』

昭和20年、西古見の武装解除時の記録には、
『繋船場跡』から砲弾を海中投棄するため、船に積み込んでいる様子が残されています。

『陸軍兵舎跡』
文献資料等を手に、一つずつ戦争遺跡を調査してみると、
建物の役割や他施設との関連が見えてきそうです。
奄美大島で『戦争』が、起こった事実を
どのように、そして、どこまで伝えていくことができるのか?
まだまだ調査は手探り状態ですが、
膨大な資料と照らし合わせながら、
今後も現地調査を進めていきたいと思います。
2014.09.09
瀬戸内町立図書館・郷土館
埋蔵文化財調査員 正 智子
2014年09月22日
「ふてぃむちと型菓子作り」 あまみしま博覧会2014夏
平成26年8月22日
あまみシマ博覧会 「親子でdo(どぅ?)ふてぃむち体験do(どぅ?)」
が,瀬戸内町中央公民会で開催されました。
あまみシマ博覧会2014夏

参加者は3歳~79歳まで!
定員を上回る参加者で,ワイワイ・ガヤガヤ楽しくお菓子作りを楽しみました。
(主催者:わ―きゃシマ未来像検討会)
関連記事はこちら → 「昔なつかしいお盆料理教室」
***
まずは,「フティムチ作り」
「フティムチ」 とは,蓬餅(よもぎもち) のこと。
ムチガシャ(クマタケランの葉)で包んだ餅のことをいいます。
カシャの葉の詳細について → 「サネンのサマリのさわり」
まずはカシャの葉を洗います。

そして,葉をハサミで切っていきます。

次は,ペースト状にしたヨモギ(下ゆで済)と黒糖粉,餅米粉,水を入れこねた餅を丸めて葉で包みます。

そして,蒸し器へ。

さぁ,蒸しあがったかな~。

蒸し時間は約30分。
調理室は,フティムチの良い香りでいっぱいに。

葉の色が青々した緑色から,しょんぼりした緑色へと変わっていますね。
続きまして,「型菓子(かたがし)」作り。
別名「むすこ」ともいいます。
一昔前はお盆前になると,各家々で作られていた「型菓子」。
(「型菓子」はお盆のお供え品のひとつなのです)
最近では,型菓子を作るご家庭も少なくなっています。
今回の材料は 菓子粉と水あめ,黒糖粉,白砂糖(上白糖),黒糖焼酎,お湯 です。
まずは,菓子粉と黒糖粉をふるいにかけます。

そして,混ぜ混ぜ。
霧吹き(お湯,水あめ,黒糖焼酎)を掛けながら,さらに混ぜ混ぜ。
ここで全体がしっとりするまで混ぜ合わせていきます。

木型にしっかりと材料を押し詰めていき,表面を平らにしていきます。

余分な材料を落とし,麺棒で木型を「こんこん」と叩いて,型離れをよくします。
まずは、講師の「川上節子」さんがお手本。

木型をひっくり返して・・・ドキドキ

上手にできました! 良かったね!

今回は黒糖の他,白砂糖の型菓子も作りました。
白,黒,ミックスと,見た目にも味があっていいですね。

****
お菓子作りが終わると,参加者全員での試食タイム!

主催者の方から,マンゴー&パッション・ゼリーとピーナッツ味噌のプレゼントも!
これも手作り。とっても美味しかったです(ありがとうございました)。




8月の熱気ただよう調理室の中でしたが,
参加された皆さんは,シマのお菓子作りをとても楽しんでいました。
「食」 から知るシマの魅力,また体感して欲しいですね。
2014.9.20
古仁屋
埋蔵文化財調査員 鼎さつき
あまみシマ博覧会 「親子でdo(どぅ?)ふてぃむち体験do(どぅ?)」
が,瀬戸内町中央公民会で開催されました。
あまみシマ博覧会2014夏
参加者は3歳~79歳まで!
定員を上回る参加者で,ワイワイ・ガヤガヤ楽しくお菓子作りを楽しみました。
(主催者:わ―きゃシマ未来像検討会)
関連記事はこちら → 「昔なつかしいお盆料理教室」
***
まずは,「フティムチ作り」
「フティムチ」 とは,蓬餅(よもぎもち) のこと。
ムチガシャ(クマタケランの葉)で包んだ餅のことをいいます。
カシャの葉の詳細について → 「サネンのサマリのさわり」
まずはカシャの葉を洗います。
そして,葉をハサミで切っていきます。
次は,ペースト状にしたヨモギ(下ゆで済)と黒糖粉,餅米粉,水を入れこねた餅を丸めて葉で包みます。
そして,蒸し器へ。
さぁ,蒸しあがったかな~。
蒸し時間は約30分。
調理室は,フティムチの良い香りでいっぱいに。
葉の色が青々した緑色から,しょんぼりした緑色へと変わっていますね。
続きまして,「型菓子(かたがし)」作り。
別名「むすこ」ともいいます。
一昔前はお盆前になると,各家々で作られていた「型菓子」。
(「型菓子」はお盆のお供え品のひとつなのです)
最近では,型菓子を作るご家庭も少なくなっています。
今回の材料は 菓子粉と水あめ,黒糖粉,白砂糖(上白糖),黒糖焼酎,お湯 です。
まずは,菓子粉と黒糖粉をふるいにかけます。
そして,混ぜ混ぜ。
霧吹き(お湯,水あめ,黒糖焼酎)を掛けながら,さらに混ぜ混ぜ。
ここで全体がしっとりするまで混ぜ合わせていきます。
木型にしっかりと材料を押し詰めていき,表面を平らにしていきます。
余分な材料を落とし,麺棒で木型を「こんこん」と叩いて,型離れをよくします。
まずは、講師の「川上節子」さんがお手本。
木型をひっくり返して・・・ドキドキ
上手にできました! 良かったね!
今回は黒糖の他,白砂糖の型菓子も作りました。
白,黒,ミックスと,見た目にも味があっていいですね。
****
お菓子作りが終わると,参加者全員での試食タイム!
主催者の方から,マンゴー&パッション・ゼリーとピーナッツ味噌のプレゼントも!
これも手作り。とっても美味しかったです(ありがとうございました)。
8月の熱気ただよう調理室の中でしたが,
参加された皆さんは,シマのお菓子作りをとても楽しんでいました。
「食」 から知るシマの魅力,また体感して欲しいですね。
2014.9.20
古仁屋
埋蔵文化財調査員 鼎さつき